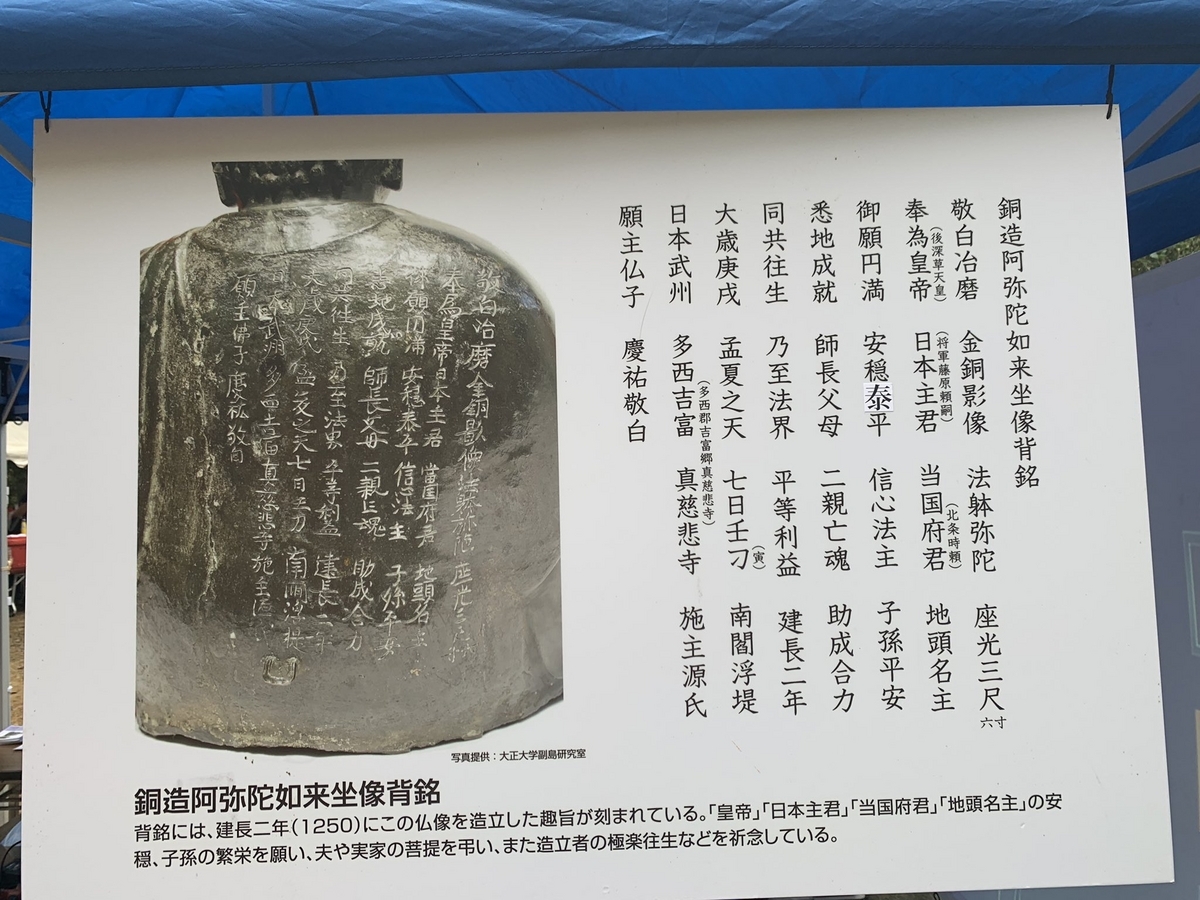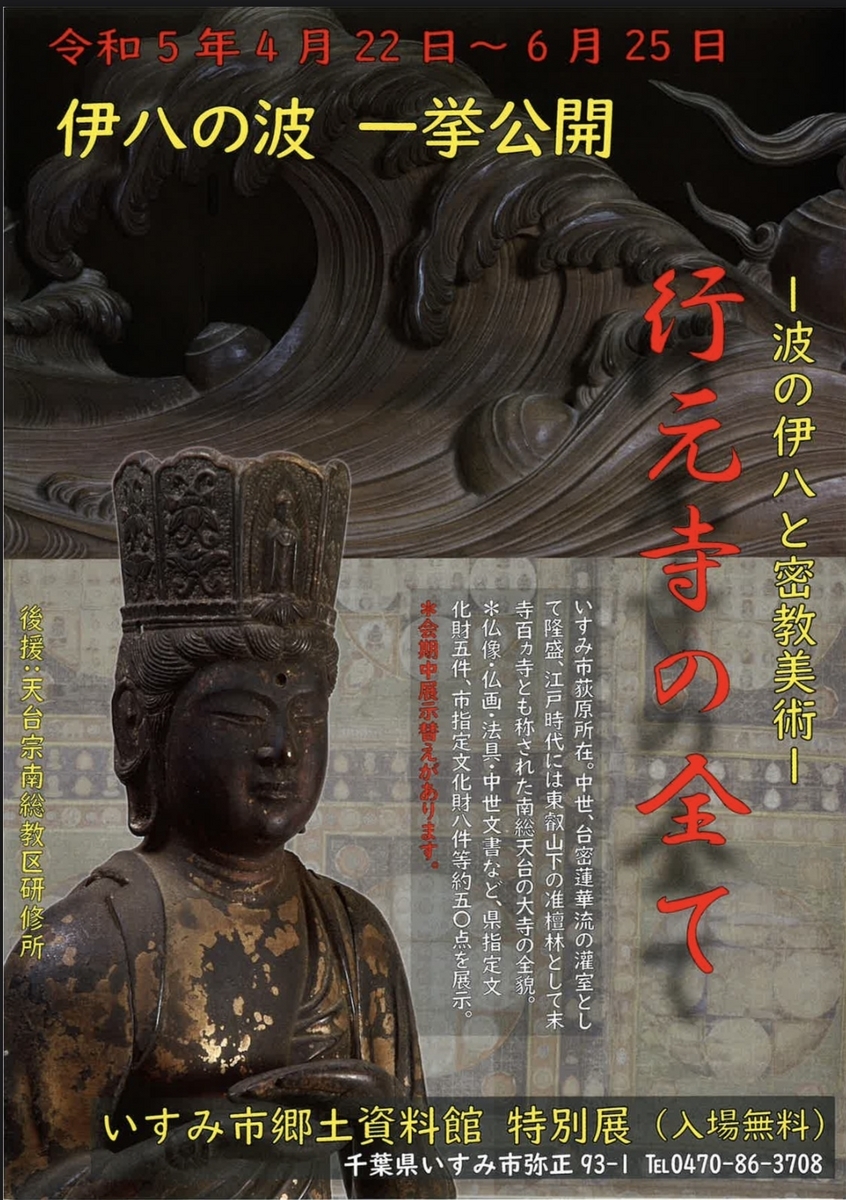仏像のブログを書き始めたのは、2005年の年末でした。最初の投稿はこんな感じ。
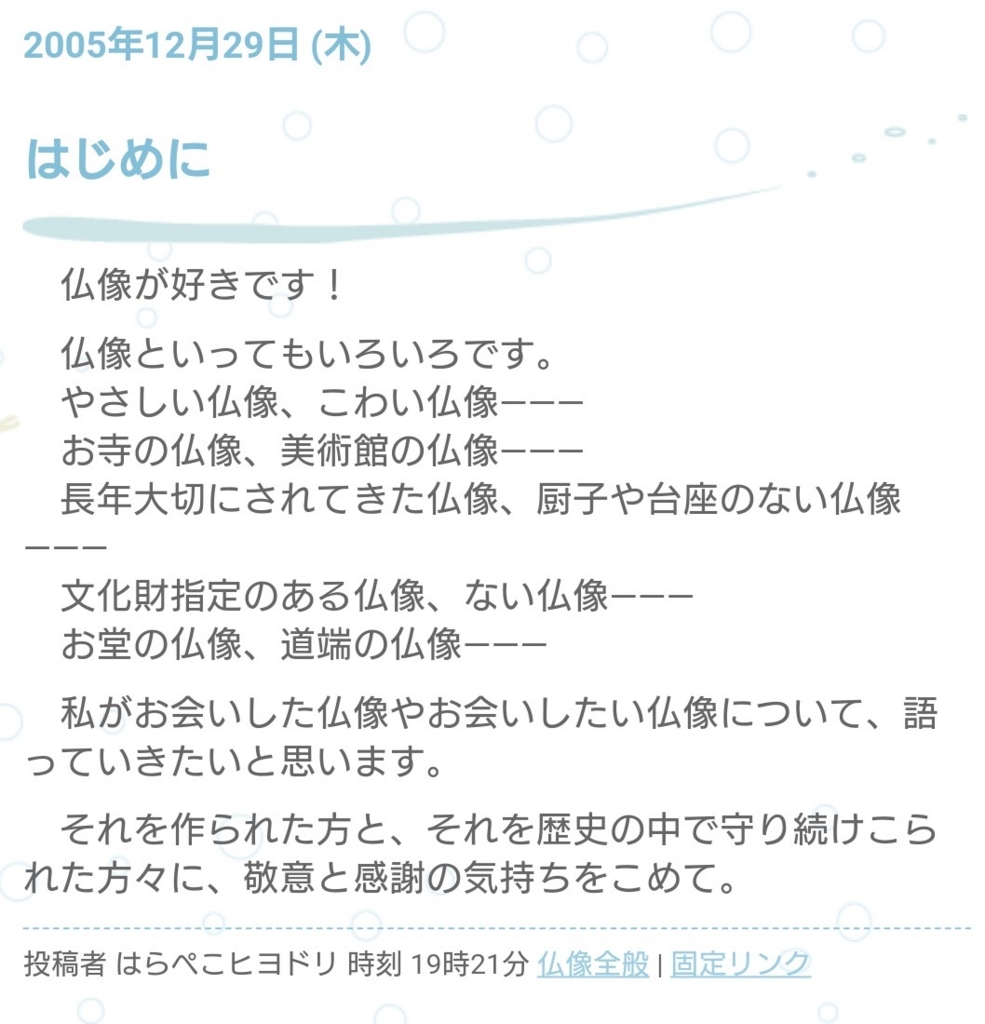
10年以上が過ぎてもこの気持ちに変わりありません。ますます仏像に魅了されています。
上記のブログは「ココログ」で書いていたのですが、投稿に無駄な手間暇がかかるのが悩みでした。
これからこちらの「はてなブログ」でお世話になろうと思います。
過去の記録は以下からご覧ください。
hiyodori-art2.cocolog-nifty.com
ブログを書いている「はらぺこヒヨドリ」さんのプロフィールは
はらぺこヒヨドリ をご覧ください。
素人の雑文ですが、これからも仏像への愛を叫んでいければと思っています。平凡な中にも山あり谷ありの人生ですが、仏像が好きなおかげでとても救われています。
仏像好きなみなさん、一緒に「仏像大好き~♪」と叫びましょう。仏像とそれを守られてきた皆様に感謝を伝えたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。